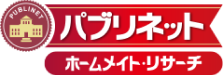足利義政
祖父にあたる足利義満が建立した金閣寺(鹿苑寺)にならって、足利義政によって作られたお寺。金閣寺の舎利殿は大量の金箔によって豪華絢爛な見た目となっているが、銀閣寺の舎利殿は銀とは名がついているが、すこし地味な茶色っぽい見た目となっている。これには理由が諸説あるが、その中のひとつはシンプルに資金が足りなかったこと。そしてもうひとつは足利義政の人柄が関係してくる。彼は元々わび・さびをとても大事にしている人だといわれていた。わびはシンプル、さびは趣のある、という意味であり。現在の日本庭園ではとても重要とされている文化である。わび・さびを重んじる足利義政にとって、銀箔を貼りギラギラさせた建物は気に入らなかったのではないかと言われている。このような理由から銀閣寺の舎利殿は銀色でないのだが、その代わりに壁面にはうるしが丁寧に塗られている。夜になると、池の水に月の光が反射してうるしにあたり、舎利殿がまるで銀色に輝いて見えるという。その他にも見どことは多く、銀閣寺は砂を多く使った庭園が有名。銀閣寺の本殿の手前は池の水がないのだが、その代わりにぎんしゃだんという砂で模様が描かれた砂場がある。これは波をイメージした模様になっていて、まるで本殿の手前まで水が来ているかのように見せている。また、向月台と呼ばれる富士山型の大きな砂山があり、足利義政はその砂山のてっぺんに座り、東山から登る月を眺めていたとされている。銀閣寺が建てられている東山を少し登ると、湧き水があるのだが、足利義政は実際にその水を使いお茶を立てていたという。ちなみに現在でもその水
使ってお茶を飲むことが出来、そのためのイベントも開かれている。また山腹には被爆アオギリと呼ばれる気を見ることも出来る。広島の原爆の被害にあってもなお枯れずに残ったアオギリの樹が銀閣寺の山腹に移植されたもの。拝観を終えても参道は清水坂のように立ち並ぶ売店で買い物を楽しむことができる。